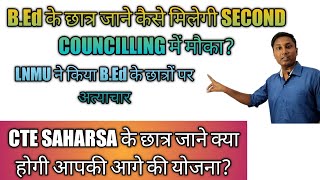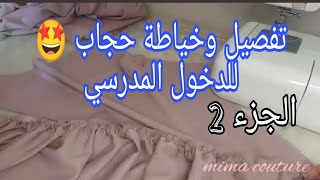Duration 15:20
ドクター力丸の人工呼吸管理のオキテ 第8回 - 臨床医学チャンネルCareNeTV
Published 10 Jan 2013
★CareNeTVはコチラ→ https://carenetv.carenet.com/series.php?series_id=73&keiro=yb_setsumei 欧米では原則トレーニングコースを修了したものしか扱うことはできない人工呼吸器。しかし、日本では特にトレーニング受けることもなく、「何となく」、使っているのが現状です。そんなお粗末な人工呼吸管理の実体に一石を投じるべく、各地で講演やセミナーを繰り返す古川力丸先生のレクチャーをアニメーションでお送りします。分かりやすい酸素化、換気の考え方。呼吸仕事量については他に例のない全くのオリジナル。実際の設定の仕方や、問題への具体的な対応も解説します。 講演ではベテラン呼吸器科医もメモを取るという斬新でオリジナリティに溢れる実用的な内容でありながら、中高生レベルの学力でも理解できる分かりやすさです。通常、数式だらけの呼吸生理学を学ぶ必要もいっさいなし。研修医、ナースとの対話形式で古川力丸先生がやさしく人工呼吸管理を解説します。 【動画の目次】 0:10 呼吸仕事量過多を見極める 2:10 呼吸仕事量は何を指標にする? 7:07 気道内圧を波形を見るポイント 9:08 呼吸仕事量過多3つのパターン 13:22 呼吸仕事量過多を気道内圧波形から読み取る 【ドクター力丸の人工呼吸管理のオキテ(全14回)】 第1回 「その挿管、なんのため?人工呼吸管理の目的」 第2回 「サチュレーション100%なら安心?酸素化の正しい評価」 第3回 「PF比を使いこなせ!正しい吸入酸素濃度の設定」 第4回 「PEEPを上げろ!酸素化を改善するもう一つの方法」 第5回 「上げ下げ簡単、PaCO2…換気の調整の仕方」 第6回 「すぐわかる動脈血ガス分析…酸塩基平衡を見極めろ!」 第7回 「換気するべき?しないべき?PaCO2コントロールの考え方」 コラム1 「先生、“逆転”しました!」 第8回 「知れば簡単!気道内圧波形…呼吸仕事量過多を見極める(1)」 第9回 「気道内圧波形に異常あり!呼吸仕事量過多を見極める(2)」 コラム2 「カプノメーターを使おう!」 第10回 「意外と少ない選択肢 …換気モードの設定」 コラム3 「初期設定総まとめ」 第11回 「特殊病態に気をつけろ! …プラトー圧とAutoPEEP」 【講師情報】 古川 力丸(こがわ りきまる)医療法人弘仁会 板倉病院 救急診療部 2004年 日本大学医学部卒業、同学附属板橋病院初期臨床研修医 2006年より救急医学系救急集中治療医学分野 救急専門医、米国集中治療医学会(SCCM)認定Fundamental Critical Care Support(FCCS)インストラクター、米国心臓病学会(AHA)認定BLS(蘇生基礎コース)インストラクター、PALS(小児蘇生コース)インストラクター、日本予防医学リスクマネージメント学会医療安全ファシリテーター 【内容紹介】 第8回 知れば簡単!気道内圧波形…呼吸仕事量過多を見極める(1) 人工呼吸管理の4つの目的のうち、「呼吸仕事量の軽減」は、臨床現場でもっとも曖昧に捉えられています。「患者さんが苦しそうだから挿管しちゃったけど、何が問題だったの?」そんなことがないように、呼吸仕事量過多の原因をしっかり把握できるようになりましょう。そのために理解しなければいけないのが人工呼吸器の気道内圧波形。難しい理論はいりません、波形のパターンを覚えるだけですぐに呼吸仕事量過多の原因がわかります! 他の回の内容紹介はコチラ→ https://carenetv.carenet.com/series.php?series_id=73&keiro=yb_setsumei ★上記番組含み1900番組以上の番組が見放題! 医療動画配信サービス「CareNeTVプレミアム」→ http://carenetv.carenet.com/lp/free?keiro=yb_setsumei 【動画テキストダイジェスト】 さて今回の「人工呼吸管理のオキテ」は呼吸仕事量の話です。呼吸仕事量を軽減することは人工呼吸管理をするにあたっての重要な目的のひとつであると一番最初に話しました。人工呼吸管理の目的は、酸素化の改善、換気の改善、呼吸仕事量の軽減、気道の確保、この4つです。この呼吸仕事量が実際の臨床現場ではとても曖昧で漠然として、よくわからない捉え方をされています。例えば患者さんが「ゼーゼーハーハー」して呼吸がつらそう、呼吸仕事量が過多だからって人工呼吸器をつけます。こういう状況、結構ありますよね。 でも、ここで問題になるのはそういう患者さんは人工呼吸器をつけるとすぐに良くなる、割と楽になるということが多いことです。あとになってこの人、呼吸仕事量が本当に上昇していたの?とか、挿管したけど人工呼吸器をつけなくても粘れたのでは?と、挿管したけど何が問題だったかわからないと言われることが結構あります。そうするとウイニングつまり離脱に持っていっていいのかどうか、これが分かんないことになってしまいます。 1回目で話したように人工呼吸管理には目的があって、その目的が達成されてるかどうかを確認することが重要です。そして、悪化をきたしていた原因を見つけて除去する努力をします。当然、これは呼吸仕事量過多で人工呼吸器をつけた場合も同じです。単に患者さんが苦しそうだからではなくて、なぜ苦しそうになってるかをアセスメントして把握することが重要なのです。だけど今までみたいな漠然としたアプローチだと、呼吸仕事量は軽減したかどうかも呼吸仕事量過多になっていた原因がよくされたかどうかも、わからないとことになります。 それは多分、呼吸仕事量にきっちりした指標がないからではないでしょうか。酸素化はpF比、換気はPaCO2を見ればいいんだけど、呼吸仕事量は具体的に何を見て判断すればいいのかよくわからないんです。ということで、今回は僕が時間をかけて編み出した秘密のやり方をちょっとお教えします。でも、そのためにはまず理解してもらいたいことがあるんですね。 それは「気道内圧」です。PEEPのところでお話はしたんですけれども、人工呼吸器に表示されるいくつかの波形の中でぜひとも皆さんに理解してほしいのがこの気道内圧の波形になります。この気道内圧の波形もちょっと理解してもらうと、呼吸仕事量が簡単にわかるようになるんですね。これはですね、気道内圧を表す式、つまりこの波形を表す式なんですけど一緒に説明するとわかりやすいからここに出してみました。 この波形が表すものには4つの代表的な気道内圧があります。1つめはPEEPです。一番下のベースラインの所がPEEPと酸素化のところで教わりました。呼気終末陽圧、呼気が終わった後にもかけている圧ですよね。そして、もう一つが平均気道内圧。これは波形全部を積算した平均値のことです。平均気道内圧が上がれば酸素化が良くなる、ただ平均気道内圧を調整すると換気まで巻き込んでしまうから便宜上、PEEPで管理をするという話をしました。 そしてもう1つ、このピンとしたところ、寝グセのところですね。ここを最高気道内圧といいます。ここは吸気の一番最初になります。人工呼吸器から送られた空気というのは人工呼吸器の回路を通って、細い気管チューブを通って、さらに患者さんの気道を通って最終的に肺胞にたどり着きます。だけど細い細い通り道をくぐり抜けてくることで、どうしても一番最初は圧がオーバーシュートしてしまう。これがここのピンと立った寝グセの部分になります。ということは、この寝グセの部分、最高気道内圧は気道抵抗を表してることになります。 例えば、気管支喘息などで気道が細くなっていると当然、気道抵抗が大きくなりますんでオーバーシュートする部分が大きくなってきます。患者さんの気道だけではないです。例えば、人工呼吸器のチューブを踏んづけたら気道抵抗が大きくなって、ここの寝グセの部分がピンと跳ね上がってきます。 PEEP、平均気道内圧、最高気道内圧、もう1つは寝グセの次に現れるここ、平らな部分。プラトー圧といいます。人工呼吸器は一回換気量、例えば500cc入れて実はその後、回路を閉じるんですね。つまり空気を送った後に入口と出口を塞いで平衡に達した時の圧、これをプラトー圧といいます。この部分が実際に肺胞にかかる圧になるんですね。そうするとプラトー圧が高くなるということは何を意味してるか分かりますか。プラトー圧が高いほど肺胞に空気が入りにくいってことだと思うから、肺が悪いってことでしょうか。そんなとこですね。 先ほどピンとした部分は気道抵抗という話をしましたが、ここのPEEPからプラトー圧まで、ここの正味上がった圧っていうのが肺の状況を表すんですね。この圧が高くなることをコンプライアンスが低下してるという風には一般的には表現されるんですね。 コンプライアンスは普通、服薬コンプライアンスとか約束を守るみたいな意味ですよね。この場合は弾性コンプライアンス、つまり物体の変形のしやすさという意味です。コンプライアンスというのは肺の広がりやすさと考えてもらうとわかりやすいと思います。コンプライアンスが低いということは肺が広がりにくい、僕たちはこれを「肺が固い」って表現することが多いです。肺が固くて広がりにくいことをイメージしてみてください。つまり、プラトー圧っていうのは肺の硬さを表してるとことになります。 これは臨床的にはどんな病態なんですか。よく見るのは無気肺ですね。肺胞が潰れて空気が入りにくい状況。あとは肺だけじゃなくて胸郭に問題がある場合。肺がうまく広がらないとかそういう時にもプラトー圧が上がってくるだろうということになります。そんな状況を総称して肺が固いっていうに僕たちはいいます。いろいろな原因がありますので、これについてはまた後でお話をさせてもらいます。 さて、ここまでをまとめると気道内圧には4つあって、平均気道内圧、PEEP、 最高気道内圧それからプラトー圧があります。気道内圧の波形を見る時にはこの4つを意識してください。じゃあ、先ほどの式。波形の意味が分かっていればこの式もすごく簡単でわかりやすいものになります。「P」というのは気道内圧を表します。「P=R×F+TV/C+PEEP」、たしかにとっつきにくい式ですよね。これを、気道内圧の波形と合わせて見てもらいたいのですが、R×Fの部分がオーバーシュートしてる部分、つまりプラトー圧から最高気道内圧までの部分になります。R×Fが寝グセの所ということです。 次がTV(Tidal Volume)/C(コンプライアンス)。これを表すのがPEEPからプラトー圧まで、一番最初のオーバーシュートした部分を除いて、正味どのくらい上がったか、この圧を表します。PEEPはいいですよね、自分たちが設定するベースラインの圧なので。この3つ、これを合わせて気道内圧の構成要素になります。 この気道内圧の波形こそが呼吸仕事量を見る上での重要な指標になります。この式の「R×F+TV/C」、ここの部分が呼吸仕事量を表すといわれています。とはいえ、計算する必要はまったくありません。そもそもこの式を覚える必要もないのです。結論から言うと呼吸仕事量が過多という時には実は3つのパターンがあります。それがこの呼吸仕事量の式からわかる、それだけ覚えて欲しいということです。まず1つ目はR×Fが上昇するパターン。このパターンというのは気道抵抗に異常があって呼吸仕事量が増えたということです。もう1つはTV/C、この部分が上昇するパターン。つまり肺の固さ、コンプライアンスに異常があって呼吸仕事量が上昇していることになります。 #古川力丸 #人工呼吸 #人工呼吸器 制作・著作:株式会社ケアネット
Category
Show more
Comments - 5